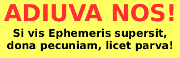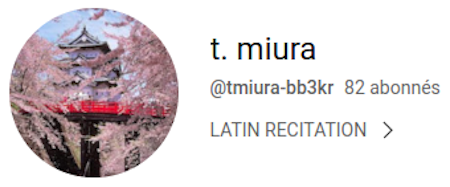ACROAMATA LATINA
Hic praebentur acroamata (vulgo: podcasts) varia quae in rete inveniri possunt. Certe opiniones hic expressae externae sunt Ephemeridi.
t. miura
Recitationes latinae
Recitation (Aenēis 2.345-360) and Slides_Recitation_激しい空腹の群狼を駆り出す様が邪悪であり後に残される子狼らが喉を渇しているとは何を意味するのか
《和訳》 【2.345 (怒りと愛のはざまで神々に己の平穏な生を滅ぼされた)不幸な者よ!(愛ゆえの狂気から敵刃へ突入して果てる彼の定めを予知した)婚約者が気も狂わんばかりに教え諭す(その正しい)声が、】 【2.346 (我らへの神の呪いゆえに、仲間となった彼の)心に(も)届かなかったとは!】 【2.347 私は、密集隊形を取っている彼らを見まわし、戦いへ心を燃やしているのが分かったとき、】 【2.348 (共に不退転の死地へ向かうべく)さらに(煽るように)こう語り出す「若者たちよ、この上なく勇敢ながらも、発揮できない悔しさを秘めたる】 【2.349 勇者たちよ。私は、その先はない戦いに敢えて飛び込もうとしている。もし、その私に賛同し同行しようとする、祖国への神がかった「愛の欲求」が君たちにも】 【2.350 確かにあるならば、(ユッピテルが定めたこの末期の)局面で、(敢えて戦う者を待つ)女神の運不運がいかなるものなのか、それを君たちは見て取ることになる。】 【2.351 (今、滅びの劫火が燃え、)彼らは皆、(我らの捧げた)至聖所や祭壇から出て行ってしまった(、トロイアを守り手なしに捨て置いて)。】 【2.352 (この)国と統治がそれによって立っていた(守護の)神々がだ。(しかるに、逆に君たちは彼らが見捨て)滅びの火を放たれたその都へ駆けつけているのだ。】 【2.353 死のう(祖国と共に、この労苦に美しい終わりを告げて)。さあ、戦いのまっただ中へ突進しようではないか。】 【2.354 我ら敗北の神命が下った者の(個人の/民族の)「(名誉を/ピエタ―スを)救う」/「生存・存続する」(可能性)は、ただ一つ、(逃げず・定めの死を恐れず)決して生存・存続を望まないこと(―敵/神々を動かす、その潔い獅子奮迅の戦いぶり―)にある。】 【2.355 このように(私の口が語っていた言葉によって)、若者たちの精神に狂気が上積みされた。我らは、その瞬間から、まさに(生きたまま)狼となって、】 【2.356 餌食を夜の靄の中で求めるようであった。すなわち、その狼らは、激しい飢餓が呼び込んだ】 【2.357'[反トロイアのユーノー視点] 邪悪な猛り狂いゆえに(小賢しい)分別には蓋をして、それが追い立てるままに跳び出し、そうして残っている子らさえも】 【2.358'[反トロイアのユーノー視点] 血の肉に飢えて待っている。まさに我らは、そのような(ミュルミドネス族のような狂暴無比の血筋の)者として、槍衾を通り抜け、敵の中を通り抜けて】 【2.357''[親トロイアのウェヌス視点] 邪悪な(ユーノーの)猛り狂いゆえに(慈しむべき子らが)見えなくなり、それが追い立てるままに跳び出し、そうして後に(守り手なしに)置き去りにされた子らは】 【2.358''[親トロイアのウェヌス視点] (今や内なる劫火に焼かれようとし、水に)渇して待っている。まさに我らは、そのような(人間を失った)者として、槍衾を通り抜け、敵の中を通り抜けて】 【2.358'''[ラティウムでの新生をにらむポエブス視点] (今や内なる劫火に焼かれようとし、水に)渇して待っている。まさに我らは、その(神の怒りと「疫病」を鎮めるための犠牲として、生きながら、「略奪者たる狼」となり裸足で「火」を渡るエトルーリアはソーラクテのアポッロー神官団の)ように、槍衾を通り抜け、敵の中を通り抜けて】 【2.359 確実な死へと、ためらいもなく突き進む。その目指すところは、】 【2.360 都の中心。我らの周囲では、(ユーノーの神威で)黒い夜の闇が飛び回り、我らを影の中に包み込む(邪魔されず死に場所に着けるようにと)。 《重要な含意》 2.355-358の、死への狂気で反撃と殺戮に向かうアエネーアースらを群狼に例える背後には、『農耕詩』第3巻エピローグと『事物の本性について』第6巻エピローグの「広く地域の生き物を『その体内の劫火』で焼き尽くす伝染病のエピソード」が潜んでいるのではないか。 一般的には「飢餓が異常な狂暴性を群狼に与え、加えて喉を乾かせて(=腹を空かせ血肉に飢えて)待っている子供らへの親心が一層狂暴性を高めている。そのように狂暴となったアエネーアースらは敵にとって恐るべき戦闘力を備えるに至った」と解釈されるであろう。 この一般的解釈には、次のような違和感を覚えた。 1)少なくともアエネーアースは、我が子の窮状を救うために何かを持ち帰るために出撃しているのではない。自分のために、戦場での美しい死で戦士としての誉れを挙げようと片道切符で出撃している。 2)後の展開では、高まった戦闘力ゆえに敵を正面から撃破してゆく場面は描かれない。状況は逆である。ギリシア兵が仲間と勘違いしたための緒戦の勝利と、それにヒントを得ただまし討ち(ギリシア兵への変装)での勝利である。しかもその変装作戦は皮肉にも味方のトロイア兵の攻撃に遭い、敵のギリシア兵には見破られ元気な仲間は全滅して終わる。 3)ウェルギリウスの他の2作品『牧歌』と『農耕詩』での狼の描かれ方を検索すると、狼が襲うのは「抵抗するすべのない、か弱い家畜の『羊』」であって、「ギリシア兵」のような「逆襲で殺され得る」強敵ではない。※『アエネーイス』11.809-813では牧人や大牛を倒した狼が出てくるが、大それたことをしたと森へ尻尾を巻いて逃げ込んでいる。 一方、次の点から狼と「伝染病」との連関が感じられる。 1)6)『アエネーイス』第11巻で狩猟の女神ディアーナに愛されるカミッラがエトルーリア人のアルンスの槍に倒れる展開の中で語られる「聖なるソラクテの守護神アポッローとその崇拝者[11.785-786]」の縁起は示唆的である。すなわち、神官団がエトルーリア語で「狼(ヒルピ)」と呼ばれるようになった由来であって「火にかけてあった犠牲獣の内臓を狼がかすめ取り神官が追いかけたところ狼は洞窟に逃げ込んだのだが、今度はその洞窟から伝染病が外に出て来てしまった。最終、その伝染病は神官が狼になることでおさまった。(岡道男・高橋宏幸訳『アエネーイス』、訳注、P.546)」というものである。 2)『農耕詩』第3巻エピローグ537-539に「より深刻な心配(伝染病による死)が狼を抑制し、羊の群れの周囲を夜にうろつかなくなる」との記述がある。 3)『農耕詩』第3巻エピローグ478-485に「暑さ:aestus」、「火のような喉の乾き:ignea sitis」という記述がある。 4)『事物の本性について』第6巻エピローグ1219-1222に「狂暴な野獣の類も森から出てこなかった:nec tristia saecla ferārum exībant silvīs」、「大部分は病気で弱って死んでいった:languēbant plēraque morbō et moriēbantur.」の記述がある。 5)出撃したアエネーアースらが最初に遭遇するのは敵兵ではなく、路上に、そして住居や神殿の戸口に無数に味方も敵もなく惨たらしく転がる死体の数々である(2.364-369)。この状況は、『事物の本性について』第6巻エピローグ1251-1270の、都市に(とりわけ神殿に)溢れる死体の数々の描写と類似である。 6)2.358の「子らが喉を乾かしている」のは、残された子狼がその後で伝染病に感染して死が迫っているとも解釈できる。さらに韻律的には、その2.358の主韻律「DSSSDS」は、下記の内容のLucr. 1218および1222の主韻律と同一である。 ・Lucr. 12.1218 DSSSDS「aut, ubi| gustā|rat, lan|guēbat| morte pro|pinquā.([死肉を]試し食いしたとき、間近に迫った死で衰弱していった)」 ・Lucr. 12.1222 DSSSDS「et mori|ēban|tur. cum |prīmīs fīda canum vīs ([1221大部分は病気で弱って]死んでいった。とりわけ忠実たらんとする犬たちの(生きる)力は[1223無念にも打倒され、あらゆる道でその呼吸を終わらせていた]) このような解釈のメリットとして次のように考える。 1)具体的次元では差異のある群狼の状況が、上位概念ではアエネーアースたちの状況と一致し適切な例えとなる。 ・共に、出発目的は自分自身の強い渇欲を満たすこと→「アエネーアース:復讐と名誉への渇欲」と「群狼:食い物への渇欲」 ・共に、ユッピテルの与えた滅亡と死滅の運命への抗いという性格を持つ→「アエネーアースたち:トロイア人勇士として、敗北と逃避による名誉喪失へ抵抗する」と「群狼:餓死による命の喪失へ本能的に抵抗する」 ・共に、残した子らに、ユッピテルの神意による死の危機が迫っている→「アエネーアース:アスカ二ウスにギリシア兵の殺戮が迫っている(今はウェヌスがそれを防いでいる)」と「群狼:子らを伝染病が侵し始めている」 2)大量殺戮をもたらすユッピテルの「無慈悲」が、2つの対照的破壊様式の対となって、余すところなく問題提起される。 ・物理的破壊(破壊者が目に見え音にも聞こえる):身体外部からの戦争の「劫火」で焼き尽くす。すでに2.304-308でギリシア軍団が侵攻する様は、農場へのユッピテルの打撃に例えられ、その背後には『農耕詩』第1巻325-334の記述が暗示されていた。 ・生化学的破壊(破壊者が目に見えず音にも聞こえない):身体内部からの伝染病の「劫火」で焼き尽くす。 詩人の意図としては次のように考える。 1)『事物の本性について』第6巻エピローグと『農耕詩』第3巻エピローグにおける「伝染病の悲惨」は通底している。ルクレーティウスの原子論は、神殿に人間の善悪に無関係な(むしろ善人ほど看病で感染する)病死体があふれる様をもって「これでも神々は関与すると信じるのか!」と矛盾を突きつけて終わる。それに対し、それを統合するために、まず第2巻で「ユッピテルが神意で関与し、その悲惨を人間たちにもたらした」ことを述べ、次に第6巻で、人間の魂の本質的救済への「神的=自然の摂理的」な仕組みと、世界の恒久平和へのユッピテルの長期ビジョン(その概要は第1巻261-296でウェヌスに開陳済み)を支えるべく用意されている将来の人間たちの魂の連綿たる様が示される。 2)人間(社会)を滅ぼす「劫火」で、むしろ恐ろしいのは「内なる劫火」であることを読者に思い起こさせる。「内なる劫火」を「強欲が心にもたらす劫火」と読み替えれば、「強欲の劫火」は外目に見えず音にも聞こえないが、確実に個人を、その個人が関わる他人を、ひいてはその社会全体に「伝染して」むしばみ、やがては「戦争」を引き起こす。ゆえに、強欲の滅却は伝統的敬神でも、原子論でも共通の目標であった。 「内なる劫火」に思いを至らすに最も相応しい場は、一国の国民全体が滅びの劫火で壊滅的に死ぬというトロイア滅亡の場面であり、第2巻でこのことを示唆することの根拠となるだろう。 アエネーアースの「不確かなあるべき未来と、それへの長期で確実な労苦の数々」を拒否し、「トロイア人勇士としての最後の大きな名誉を確実に得るために、一瞬の労苦たる死を選ぶ」という「内なる劫火」は、若者らに伝染し、彼らは狂気に「燃える集団」となった(2.347, 2.355)。このような一見勇ましいが、集団に害毒を流し実は神意に反する考えへの誘惑に対して、いかに抵抗するか、あるいは身をゆだねるのか。正しい神意の道とはいかなる道なのか。第2巻でそれを提起し、全巻エピローグのトゥルヌスの死までをかけて、詩人はアエネーアースらの具体的行動を通して語るのであろう。 ※同じ出陣する群狼でも、『イーリアス』 I. 16.155-167のミュルミドネス族と『アエネーイス』 A. 2.355-360のアエネーアースと若者たちの、似て非なる様の考察は動画スライドの12/18-16/18を参照。 以上
23 views • Jul 21, 2024
Recitation_『アエネーイス』第2巻_韻律の体感_DSDSDD|APAPAA_共通の主と従の協調韻律で歌う「2.329 victor Sinōn」に至るまでの木馬の奸計
2.329は勝ち誇るシノーンの様を、「DSDSDD|APAPAA」の韻律で、第1脚から第4脚まで、主韻律で「D」と「S」が、それのみならず、従韻律で「A」と「P」が交互に現れ、両韻律の協調で聞く者の心を揺さぶるように歌う。ちなみに、第2巻の2.1~2.329までの範囲で、この主・従韻律を共有する詩行をリストアップすると下記の7行となる。 これらの7行は、それぞれ異なる語詞を用いつつも、主と従が協調する「DSDSDD|APAPAA」という同一の韻律を響かせる。それらをまとめて朗読することは、この韻律が持つ人の心を揺さぶる効果を体で感じることになるのではと考えた。 そしてそれは、第2巻の主題である木馬の奸計の「聞かせどころ」を、シノーンが勝ち誇る場面までたどることになるのだろう。 2_73 quō gemi|tū con|vers(ī) ani|mī com|pressus et| omnis 2.161 Trōia fi|dem, sī| vēra fe|ram, sī| magna re|pendam. 2.209 fit soni|tus spū|mante sa|lō; iam|qu(e) arva te|nēbant 2.239 sacra ca|nunt fū|nemque ma|nū con|tingere| gaudent; 2.260 reddit e|quus lae|tīque ca|vō sē| rōbore| prōmunt 2.320 sacra ma|nū vic|tōsque de|ōs par|vumque ne|pōtem 2.329 fundit e|quus vic|torque Si|nōn in|cendia| miscet ・共通韻律「DSDSDD|APAPAA」の特徴 第1脚から第4脚まで主韻律では「D」と「S」が、従韻律では「A」と「P」が交互に同期して現れ聞く者の心に揺さぶりをかける。 ・和訳 2.73:そうして、その嘆き声によって、(皆の)精神(の向き)は転じられた。そして全ての(激情)が抑制され(ユッピテルの主客の正義を取り戻し)た。 2.161:トロイアよ、すなわち(私との間の)信義を(保たねばならない)。もしも私が真実の数々を知らせるだろう、もしも私が(トロイアが守る約束の数々を)大いなる価値(を持つその真実)の数々で釣り合わせるだろうと期待するなら。 2.209:(対の大蛇の左右にくねる力で)海が泡立ち、大きな音の生じる(のが聞こえてくる)。(そのような様が続き)今や、(我らのいる)陸に着こうとしていた。 2.239:(少年・少女らは、都の祝祭気分を象徴するように木馬の)神々しさをたたえる歌を歌い、その綱に手で触れ神につながることを喜んでいる。 2.260:木馬は(夜陰に隠れて人目を避け)産み戻す。(さて内部の)彼らは「勇躍」(自ら)、樫材の(骨格で支える)空洞から現れてくる、 2.320:(老いた神官のパントゥースは、私とは真逆で、神命に従うかのように、武器ならぬ)聖具と敗れた神々の像を手にし、また幼い孫を 2.329:(武装した将兵を)木馬はどっと注ぎ出す。そして、(丸腰のたった一人で敵地に飛び込み、今、敵の中枢で仲間を増やし、これで)勝ったと喜ぶシノーンが、諸処に火を付け混乱を呼び 以上
8 views • Jun 21, 2024
Recitation (Aenēis 2.328-344) and Slides_ルクレーティウスよ、アエネーアースとその仲間には死への恐怖はない_怒りが復讐と名誉ある死を求めさせる
《和訳》 【2.328 武装を固めた将兵らを、高く城市の真ん中でそびえ立ちつつ】 【2.329 木馬はどっと注ぎ出す。そして、(一人丸腰で敵地に飛び込み、今、敵の中枢で友軍を生み増やし)勝ったと喜ぶシノーンが、諸処に火を付け混乱を呼んで】 【2.330 あざけるように跳ね回る。(木馬の将兵らが)城門を左右に開いたとき、そこに待機していた(全軍の)残る者たちは、城門を通りその姿を現す。】 【2.331 (総数では)千を単位の、以前から大いなるミュケーナエより到来していたありったけの軍勢だ。】 【2.332 その残る者たち(すなわち、城門から入った全軍)は槍を構えて通路の数々を所狭しとばかりに埋め尽くしてしまった、】 【2.333 槍衾となって。戦列は(声を立てず、ただ、光が)鉄の刃先を(妖しく、死を美しく見せるかのように)きらめかせて持ち場につく、】 【2.334 密集体形をなし、殺戮の準備が整った。[ここでパントゥースは一旦間を置き、途切れがちに再開する] (我らがその終わりを喜んだ)「戦い」は、(木馬の将兵らを使って)最初に城門の不寝番で小手調べをするやいなや、】 【2.335 (今や城内で配置についた全ギリシア軍を手先とし、殺戮を求め、敵味方の)区別が眼中になくなった軍神マルスとともに、再びしっかりと立っているのだ(もはや誰にも止められない)。】 【2.336 このように語ったオトリュスの子の(なぜか最後の一人として長らえるのは美しくないと思わせる)言葉によって、言い換えれば、神々の今や一つとなった神意(すなわち、違いをそこまではよしとした至高神のうなずき)によって】 【2.337 (逃避行ではなく)劫火の中へ、つまり戦争の渦中へと私は突き動かされる。おぞましい正義の守護者エリーニュエースの一人が(、あるいは両軍勢からそう見なされる一人が、背後のユーノーと呼吸を合わせて呼び寄せる)そこへ、】 【2.338 言い換えれば、(声を控えていた敵の大軍が、トロイアの終わりを宣言するように)天上の神々へ照覧あれとばかりに発した、うなりのような鬨の声が呼び寄せるそこへ(、守護神ではなく武器へと私の手を導いたあの鬨の声のところへ)。】 【2.339 仲間に加わってくるのは(次の5人)。リーペーウス、次に武器にかけては随一の】 【2.340 エーピュトス。続いて、ヒュパニスもデュマースも。(5人の者たちは皆、今や暗闇ではなく、ギリシア艦隊の進路を照らしつつ共に上陸した)月明りの中を通って現れてきたのだった。】 【2.341 そうして、(順次)我らの両側に一群をなしていく(、言い換えれば、やがての無駄死の輪を広げながら)。加えて、若きコロエブスも、】 【2.342 すなわち(プリュギア王)ミュグドーンの子も―彼は、当時、偶然を操る女神の神意で、たまたまトロイアへ】 【2.343 やって来て、(突如)カッサンドラへの「常軌を逸した愛」に燃え上がったのだったが...。】 ※アエネーアースよ、その逸話を想起した時、お前は妻クレウーサへの愛を、父への、子へのそれを思い起こさなかったのか。パントゥースの老爺と孫の逃避行の姿、そしてコロエブスが加わった時に彼の愛のいきさつを思い起こさせたのはウェヌスであり、お前を支配する感情をユーノーの「怒り」からウェヌスの「愛」へ転換させようという女神の意図ではなかったのか。さらに言えば、この尋常ならぬ突然の愛はトロイアをテコ入れするためのウェヌスの計らいではなかったのか。 【2.344 そうして、(婚約して)将来の婿となり、(再度)プリアムスとプリュギア人の盟約のために援助を携えてやって来ていたのだ。】 【2.345 不幸な者よ。婚約者が気も狂わんばかりに(トロイア滅亡の定めと、その渦中での彼女への愛ゆえの彼の死を、それゆえに逃避すべきと)教え諭したにも関わらず、】 【2.346 (彼女にまとわりつくポエボスの呪いゆえに)耳を塞がれていたとは!】 ※アエネーアースと類似の状況に見えて結果が逆。正しい神託を受けたこと、それでも戦闘に参加したことは同じでも、神々の好意を得て生き延びるか、悪意によって戦死するかの違いが出た。アエネーアースの一旦帰館後の状況まで含めれば、配偶者/婚約者が懸命に家族を連れての逃避を訴えたことも同じだが、神々の好意で訴えが聞き届けられるか、悪意で邪魔されるかの違いがある。 アエネーアースは、コロエブスが戦死してしまう前に、おそらく仲間に加わった際に彼からカッサンドラとのやり取りを聞いたのであろう。ヘクトルのお告げを聞いていたからにはカッサンドラが正しい教示をしており、神意の逃避行に移る選択肢もあったはずだが、すでに、トロイアの滅亡に殉死するつもりでいる彼の決心を変えることはできなかった。 また、ここにはウェルギリウスからルクレーティウスへのアンチテーゼがある。すなわち、人間は愛ゆえに死を恐れず、逃避ではなく火中へ飛び込むことがある。確かにパントゥースは死を恐れ、我を忘れて逃避した。しかしコロエブスは、やがて、カッサンドラへの愛ゆえに多勢に無勢の敵中へ突進することになる。 《重要な含意、特徴的韻律関係の意味》 (1)2.329と2.260は異なる語詞を用いつつ同一内容・同一主および従韻律でつながり、それらの内容における焦点の当て方の差異を隣接/近傍の真逆主韻律の詩行が与える 1)異なる語詞で離れた詩行同士が示す内容と韻律の一致 ・260 木馬から敵将_DSDSDD|APAPAA ・329 木馬から敵将_DSDSDD|APAPAA 260と329は同じ上位概念でありつつ焦点を当てる細部が異なり、その差異の由来は夫々の近傍の真逆主韻律で導かれる。 2.259~2.329の間に、「DSDSDD」の真逆主韻律の「SDSDDS」は、2.259、266、314の3か所に現れる。その担う意味は「主人公が戦力的に劣勢(多勢に無勢)にある状況」である。 具体的には、次のようになる。2.259:木馬内に封印されたギリシア勢、2.266:切り殺されたトロイアの城門番兵、2.314:アエネーアースの死を覚悟の出陣。 2)焦点の差異 ・260: 敵の奸計:木馬の正体→(圧倒的兵力差の側面も内包する) ・329: 敵の圧倒的兵力:木馬から出現 ※1 上記焦点の差異は、260のreddō[元に戻す]と329のfundō[どっと注ぐ]に象徴的に担われている。 ※2 敵の圧倒的兵力の内容は329のfundōの目的語armātōsが含まれる前行328とともに表されている。加えて、328の主韻律も「DSDSDD」であるため「DSDSDD」の2連続となり、「DSDSDD」の含意が強調されている。 2-1)「木馬の正体」に関わる主韻律と内容の真逆性 259 SDSDDS: 封印状態_外部から解除→(封印兵力は外に出ない限り無力) 260 DSDSDD: 解放状態_内部から出現→(解放兵力は戦力) 2-2)「敵との兵力差」に関わる主韻律と内容の真逆性 314 SDSDDS: 多勢に無勢だろうが私は戦う 329 DSDSDD: 武装将兵の奔流を木馬は吐出 (2)1.1とのキアスムス関係によって2.335の主韻律が示唆するもう一つの構文解釈「2.335: portā|rum vigi|lēs et| caecō| Marte re|sistunt.’|| SDSSDD|PPPAAA」 2.334後半-335の「vix prīmī proelia temptant| portārum vigilēs et caecō Marte resistunt.’」の典型的構文解釈(例えばPerseusの [John Dryden, Theodore C. Williams])では、下記のようになる。 ・副詞:vix(かろうじて[~する]) ・主語:vigilēs(不寝番たちは) ・動詞1:temptant(試す) ・目的語1:proelia(戦いの数々を) ・動詞2:resistunt(抵抗する) ・副詞句:caecō Marte(先の見えないむなしい戦いの中で) しかし、ここで2.335の主韻律に着目すると次のような別解釈の可能性が浮き上がる。 ・副詞:vix(etと共に、vix~et... [~するかしないかのうちに...する]) ・主語:proelia(戦いの数々は) ・動詞1:temptant(試す) ・目的語1:vigilēs(不寝番たちを) ・動詞2:resistunt(再びしっかりと立つ[終結を喜んだ戦いが戻り、もはや誰にも止められない]) ・副詞句:caecō Marte(軍神は無分別となり[殺戮を求める]) 2.335の主韻律の着目点は、全巻の主題を担う1.1のそれとキアスムス関係にあること。例えば、同じキアスムス関係で第1巻および第2巻の序歌に現れる1.1-1.33、2.2-2.4の事例では、「出トロイア」-「ローマ人創出」、「祖国陥落体験の瘡蓋めくり開始」-「今もうずき返すトロイアの悲惨」のように、全巻主題にふさわしいスケール感の内容が「起」と「結」として対応している。 しかるに、2.335の内容が「不寝番の者たちが最初に襲われてかろうじて抵抗している」では、2.335に最も近いカウンターパート主韻律たる「DDSSDS」を持つ、2.293の「トロイアはお前に守護神を託す」に対してスケール不足の感が強い。「軍神の狂気に煽られた[滅亡への]戦いが、今ここに幕を切って落とされた」という内容で初めてスケール感のバランスがとれると考える。 (3)2.289と2.337の主韻律がキアスムス関係にある意味:内容の起結関係(方向性の反転) ―2.289 DDSDDS「起」:神命拝受_劫火/戦火からの脱出 Ⓧ 2.337 SDDSDD「結」:反神命の選択_劫火/戦火への突入― 内容の上位概念の対比 ・2.289【起】: 生きて「未来」と一体化する方向へ →至高神ユッピテルの約束たる栄光の再建への長く困難な道へ ※しかし無実の今の祖国を滅ぼす至高神の約束を信じられるか? ・2.337【結】: 死んで「過去」と一体化する方向へ →栄光のトロイアの最終頁を美しく飾ろう ※しかし人間は敗者の栄光を美しく記録に残すほど崇高か? カルターゴーでのアエネーアースには上記2つの対照的疑念がある/あった。 至高神ユッピテルの正義への疑念は、3.2 immeritam [罪のない]に現れ、逆に、人間の崇高さの確信(ユーノーの策略でもある)は1.459-465のユーノー神殿を飾るトロイア戦争の「実質のない絵画」を見ての感涙に現れている。 (4)2.339→340→341と段階的に、主韻律がS的からD的に、一方で従韻律がA的からP的に推移する意味 2.339: SDSSDS|AAPAAA 2.340: DSSDDD|APPAAA 2.341: DDSDDD|APPPAA ・主韻律(S的→D的):アエネーアースに同行者が次々と加わって来る、現在進行形の躍動感。 ・従韻韻律(A的→P的):結局トロイアは滅び、後の戦闘でこの5人は全員死ぬ。彼らを死へ言葉で駆り立て結果を知る者(アエネーアース)にとって、無駄に死にゆく人数が増えている。その陰鬱さの予示。 以上
19 views • Jun 16, 2024
Recitation (Aenēis 2.313-327) and Slides_ アエネーアースのピエタ―スは神命に反して祖国滅亡への殉死に向かうのか
《和訳》 【2.313 (そのとき)敵兵らのときの声とラッパの響きが重なりあって湧きおこる。】 (※これは、脱出し守護神を祭る大都を創建せよとの「神命」と憎き敵への「反撃」の間で揺れるアエネーアースを、戦いに駆り出すとどめのようであった) (※トロイアとトロイア人必滅の定めを眼前にし、至高のpietāsを備えるべきアエネーアースは、ルクレーティウスの言う死の恐怖によるpietāsの至高の徳目の腐敗[Lucr. 3.83-86]にどのように対峙していくのか。ここに全編を通じて歩むその道が始まった) 【2.314 (神々ならぬ)武器へと私は手を伸ばす。平常心は失われた。(我らの)兵力について丁寧な計算はしない。】 【2.315 そうではなく、戦いのために手勢をまとめ、本丸のに急いで集結しよう、】 【2.316 (既に馳せ参じ待っている他の)仲間と共にと、勇気が燃える。(信義を裏切ったギリシア人とそれを黙認した神々への)怒りと激情(に身を委ね、それ)が先に心を】 【2.317 捉える。そうして、(滅亡の祖国に殉じて)城を枕に討ち死にすることは美しい、(戦士として祖国への究極のpietāsだ)との思いも湧いてくる。】 (※アエネーアースの怒りと激情に乗じて、ユーノーはささやき、pietāsの名の下に、殉死を美化させた。アエネーアースはやがて覚めるべき第3の「夢物語」に入った) (※死を恐れず美化するその勇気は、至高の敬神徳目「祖国への忠と親への孝」に関わるルクレーティウスへの反論。しかし己の今の名誉しか考えない「死」は、守護神を奉じて未来を開けとの「神命」を放棄すること。また父・妻子をギリシア兵の殺戮に委ねることになる。それは最悪の不敬神ではないのか) (※一方、至高神ユッピテルの全てを包摂する神意の下、トロイアから「夜逃げ」し、漂着したアエネーアースは、今この話を語りかけ、ユーノーの神威で深い関係となるディードーから、後にユッピテルの関与で、またもや「夜逃げ」することになる。彼女は愛と信義を踏みにじる彼への怒りと激情に駆られ、テュルス人たる名誉と死による復讐のために、ユーノーさえ予期せぬ「自死」を決行する。人間集団の再創造のために、その事物の本質たる属性として切り出されたpietāsを担うアエネーアース。その彼を引き止めようとするユーノーの邪悪な「結合」は、ユッピテルによっていずれも死滅的に崩壊するのであるが、ここにおいて、その崩壊での死を選択するアエネーアースも、ディードーもルクレーティウスのいうような[Lucr. 3.71-81]人生を暗黒にした死への恐怖ゆえにそうするのではない) 【2.318 ここにおいて、(本丸へと急ぐそのとき、神々の去った神殿の奥から、)見よ、(迫り来る)ギリシア勢の殺戮から逃れる(あの)パントゥースが、】 【2.319 パントゥースはオトリュスの子として生まれ(ポエブス神の聖地デルフィーからへルクレース後のトロイア再建の神託を携え連れて来られ)た。要塞のように(これまでトロイアを守護してきた)ポエブス神の神官であった、】 (※「Othryadēs」の響きは、後のローマ人に、アエネーアースに向けて常に次の矢を用意するユーノーの不吉な予感を与えたであろう。後の世のその者は、盟約による同数300人の決戦で、負傷しつつも戦場に残った最後の一人となったが、彼は、戦士たる名誉のために「自死」を選んだ) (※パントゥースはデルフィーの神託で、場所と民族をそのままに再建することを是とした。第一次トロイア再創造の神意の担い手であったが、今、その神意を担う任務も彼から場所・民族を拡大すべき第二次再創造のアエネーアースへ移される) 【2.320 (私とは真逆で、神命に従うかのように、武器ならぬ)聖具と敗れた神々の像を手にし、また幼い孫を】 (※後のアエネーアース自身の逃避行の様のようで実は似て非なるもの。彼らに未来はあるか) 【2.321 まさに(老いて庇護されるべき最年長の)彼自身が(失われた父母に代わって)引いてくる(のが目に入る。)。彼の者は平常心を失い、走って(私のいる、神殿の)玄関口へと出てくる。】 (※ポエブス神が、この逃避行の頼りなさ、つまり、自分の死がわが父と子を死に追いやる結末の不敬神さをアエネーアースへ啓示しているようだ) (※神命遵守の手本を眼前にして心が揺らぎつつも、それでも戦士として武功を挙げ殉死しようとするアエネーアースは、意を決して尋ねる。) 【2.322 「どこに、(我らトロイア人の)『最後』の事績の『場』があるのだ、パントゥースよ。つまり我々は、どの要衝を持ちこたえているのだ。」】 【2.323 それらの言葉を話し終えるか否かのときに、彼は、呻き声と共にこのように返す。】 【2.324 「(ついに*Lucr. 1.584-585, 2.1105-1145)やって来たのだ、『最後』の『一日』が。つまり、逃れようのない(崩壊すべき万物の摂理へ向けて、始祖からの連綿たる出来事*Lucr. 1.459-468が収れんする、その)『時』が】 【2.325 トロイア人の始祖たるダルダヌス(以来のこ)の都に。ダルダヌスの孫にしてトロイアの名祖なおやトロースの子孫たる我らは、もはや在り終えた。在り終えたのだ、トロースの息子イールスの創建した(この)トロイアの都も。】 (※ウェルギリウスはルクレーティウスを統合するにあたって、事象やそれらの相互関係は取り入れる。ただ、それが自然の摂理のみの作用であるのか至高神ユッピテルの関与があるのかに違いがある) 【2.326 そしてダルダヌスの義父たるテウケルの子孫らの(この地で創建以来築き上げてきた)並々ならぬ偉大な誉れ(とその証たる富)も。全てを、ユッピテルが無慈悲にも、ギリシア人へ】 【2.327 移してしまったのだ。ギリシア人は都に火を放ち制圧している。】 (※その「無慈悲なユッピテル」は、「原子」のように、帰無ではなく螺旋的再創造のため、今はトロイアからギリシアへ移し、次にはそのギリシアからローマ/トロイアへ戻す) 《重要な含意、特徴的韻律関係の意味》 (1)『アエネーイス』へのルクレーティウス原子論統合上の最大の課題:精神を腐敗させる「死と冥界の恐怖」の克服は唯物論でのみ可能なのか? Lucr. 3.83-86とA. 2.312-315の夫々に連続4行の詩行群が、全ての行で真逆主韻律の対を作る構造は、偶然とは思えず、ここに両者の対話をみる。アエネーアースはどう行動するのか?主役は「避けんとするTimorか求めんとするAmorか(→Amorを包摂するTimorへ)」、守るべきは「現在か未来か(→未来を包摂する現在へ)」。答えの全容は、全編を通して主人公らの、高言ではなく、行動を通して示される。 (2)2.313と314の主韻律が真逆である意味 この両対だけで見れば「2.313:圧倒的敵軍の襲来」対「2.314:私の無謀な反撃開始」という対照的内容と一致しているようだが、主韻律を指標としてさかのぼると、下記のような「至高神ユッピテルの絶対的『定め』と、それに逆らう『狂気』」の関係が見出される。 ・「DSDSDD」:2.313, 2.294, 2.290 ☞「敵軍によるトロイアの滅亡が始まっている。至高神ユッピテルの神意の『連れ』として(2.294 fātōum comitēs)、お前アエネーアースは『このトロイアの守護の神々をつかめ(2.294 hōs cape)』。神々をお連れする新たな大都へ落ち延びるために」 ・「SDSDDS」:2.314 ☞「(arma āmens capiō)『つかんだ』のが『神意の神々』ではなく、『武器』であった」 さらに、ユッピテルの定めに逆らう「āmens(狂気)」の原因・背景を第1巻序歌に求めると、ユーノーの『怒り』(DSDSDD)が、加えて、ユッピテルの「ローマ」の長期ビジョンに対抗する同女神の「カルターゴー」の長期ビジョン(SDSDDS)が浮かび上がる。「DSDSDD」と「SDSDDS」の真逆性は、同じユーノーの「トロイア/ローマへの怒り」と、「カルターゴーへの慈しみ」の対照性に呼応。 ・「DSDSDD」:1.2, 1.4 ☞「至高神ユッピテルの定めによるイタリアはラーウィニウムへの(トロイア滅亡ゆえの)落人行は、トロイア滅亡から始まり到着地での安住まで(1.3のet terrīs et altōには出発の地および到着の地での受難を含むと解釈)苦難の連続であり、それはユーノーの『怒り』によるもの」 ☞「ユーノーのトロイアへの『怒り』が、ギリシア軍にトロイアを攻撃させる[2.313]」 ・「SDSDDS」:1.13☞「イタリアはティベリスの河口(から世界へ広がるであろうローマ)に、はるかに[longē]、対峙する[contrā]のはカルターゴーである。(それは、ユーノーがどこよりも慈しみ[1.15]、世界の王にと密かに図っている都[1.17]である)」 ☞「ユーノーのカルターゴーへの『慈しみ』が、アエネーアースの湧き上がる敵への怒りにつけ込んで狂気を吹き込み、武器をつかませる[2.314]。(戦場での『死』を美しいと思わせて[2.317]。※アエネーアースが戦死し、その結果、父・妻・子[イウ―ルス]は守り手を失いギリシア軍に殺害される。それで将来のローマの誕生を阻み、カルターゴーを世界の王にすることが狙い) (3)2.320と2.723は似て非なる「敬神者の逃避行」―2.320:ポエブスの神官「パントゥース」と2.723:比類なき敬神の勇士「アエネーアース」 1) 内容 2.320:アエネーアースが見入る神官パントゥース一家の敵の殺戮から逃げてくる様 「聖物と敗れた神々を手に、幼い孫を他ならぬ自身が引いている[2.321])」 2.723:アエネーアース一家が敵の殺戮から逃げる様 「(聖物と祖国の守り神を手に持った父[2.717]を、背負うために下に入る。(私の)右手へ自らを幼いイウ―ルスは(つなぐ[2.723])」 内容面では「pietāsにおいて重要であるがゆえに安全に避難させられるべき3つの存在:神々、最年長者、最年少者」のそのあり様の視点から、次のように考えられる。前半では「神々と最年長者」の立場からすれば、2.320では自分たちを庇護してくれる壮健な大人が「誰もいない」のに対して、2.723では「豪勇無双の息子がいる」という対照的状況がある。一方、後半では、「最年少者」の立場からすれば、庇護してくれる大人に手を引かれているその状況は両行で同一のものである。 2) 韻律形式 2.320: DSD+SDS|APA+PAA, 2.723: SDS+SDD|AAP+PAA 詩行の対応関係の内訳をみると、主韻律では、真逆対応の半分(前半)と同一対応の半分(後半)の合成で全体が成り立っている。同様に、従韻律でも、ほぼ真逆対応(3脚中2脚が逆)の前半と同一関係の後半で合成されている。このような「真逆」と「同一」が半分半分である様は、「似て非なる」内容関係の好適な反映といえるのではないだろうか。 3) 「似て非なる逃避行」が2.320で出現する意味 ポエブスから、落人行のアエネーアースへは、要所で重要な神託を神官等を通じて彼に示すことになる。その意味で、この段階で無駄死にしないように彼に重要な示唆があっても不思議ではない。そして、パントゥースはポエブス神殿の神官なのである。ポエブスの示唆が、神官のあり様・振る舞いに込められたのだと考える。その含意は、年老いた「最年長者(アンキーセース)」に手を引かれる「最年少者(イウ―ルス)」の無防備で、未来のない様をアエネーアースの目に焼き付ける(2.318 Ecce)ことである。 以上
34 views • May 19, 2024
Recitation (Aenēis 2.298-312) and Slides_「トロイア滅亡」の「田野への自然災害」の比喩は『農耕詩』につながりその文脈を取り込む
【和訳】 【2.298 (アエネーアースが皆と同じように偽りの現実で安らかな眠りの中におり、夢に現れた傷だらけのヘクトルにお告げをうけている)その間に、(ここアンキーセースの館からは)遠く離れて、城市には(敵の侵入した城門付近から始まった)阿鼻叫喚によって、(逃げ惑う人、様子を見に来る人、本丸へ向かう人らが交錯し)混乱が起こっている。】 【2.299 (ここにも届く)喧噪は次第に大きくなってくる。親のここは(城門や本丸から)離れて人目にも付きにくい(立地ではあった)のだが。】 【2.300 (それというのも)アンキーセースの館は、(城市の反対側にあり、)奥まって木々で隠されていたのであった。】 【2.301 (しかしまだ無事なここでも、)喧噪は、はっきり聞き取れるようになり、武器の恐ろしげな物音が耳に押し入って来る。】 【2.302 (悪夢のようなヘクトルのお告げを裏付ける物音に)夢から追い出された私は、(さらに、己の信じた現実が真か偽りかを求めて)屋根の最頂部となる稜線まで】 【2.303 (―後にかなたの家にそびえたつ火の神と対峙するとは知る由もなく―)登りつめて、(遠くまで目視しようと精いっぱい)そびえ上がる。(しかし夜の闇と樹陰がそれを妨げる。)耳をそばだて探るが、(一刻の猶予もならない様子ではあるものの、音だけでは全容がつかめない。これは現実か、実は夢だったお告げの悪夢の続きかと、開いた口を閉じるのも忘れて)呆然と立ち尽くす。】 【2.304(敬神で優れた勇士ではあるが、聞いたばかりの神意の道に未だ不慣れな、アエネーアースの様を例えるならば)、それは、(分厚い雷雲で昼なお夜の闇のごとき中で、ユッピテルの稲妻が引き起こす)火炎が、荒れ狂う南風とともに黄金の実りの畑へ】 【2.305 (抗いようもなく)襲いかかるとき、あるいは渓谷の流れが激しい鉄砲水となって、】 【2.306 (まさに)田野をなぎ倒し、その喜びの作物を、つまり、牛たちの労苦の成果をなぎ倒すとき、】 【2.307 さらには(田野の)木々を頭から激流に引き倒すとき、あたかも(労苦を要求しつつも、神々の予兆に気を配り、ケレースを大切にすることで報われるはずの、そのような農耕の神意の道に)未だ不慣れな(、優れた兵士ではあったが退役し、神の哀れみを受けるべき)牧人が呆然とするかのよう。すなわち、その者は(闇の中で事態を探ろうと)高い】 【2.308 岩(に登りそ)の頂点から、(圧倒的)破壊の物音を浴びる中で、(一刻の猶予もならない様子ではあるものの音だけでは全容がつかめず)呆然とするのみ。】 【2.309 まさにそのときであった。真実によって、(偽りを神へ誓ったあの者と、そうと知りつつ沈黙した神々の)信義が明らかになった。ギリシア人らの(夜の闇に隠されていた)それが(今)くっきりと浮かび上がったのだ、】 【2.310 邪悪なはかりごとが。(目にしたのは、パリスの死後ヘレナをめとった)デーイポブスの広大なそれが崩れ落ちたまさにその瞬間。】 【2.311 (ウェヌスの夫だが以前にはアキッレースのために母ユーノーの願いを聞いてクサントス川を火であぶった、その)火の神ウォルカーヌスが、(かかってこいと挑発するように)館の上にそびえ立つやのこと。そして直ちに次の、隣接する家が燃える。(―これは!ヘクトルのお告げのとおり、この大火事から直ちに父・妻子を守りつつ逃げるべきときか。それがpietāsか。いや待て、奥まって木々に覆われたここは、火の粉をかぶりにくく、敵も見つけにくい。まだ大丈夫だろう、むしろ祖国への...。[ユーノーの関与か、]なぜかそのように思い直す―)】 【2.312 燃えるそれはウーカレゴーンのところ。(今や人目をはばかることをやめた)猛火により、シーゲーウムの海峡は広く照らし出される(闇にまぎれた海からの脱出を断念させるように)。】 【重要な含意】 疑問:なぜ、「トロイア滅亡」の比喩に「田野への自然災害(2.304-308)」が使われるのか 理由: トロイア滅亡」に関わる文脈が、先行して世に出された『農耕詩』第1巻(穀物)の関連個所で扱われ、その参照が『アエネーイス』当該箇所を補足するため。 (1)『農耕詩』第1巻(穀物)エピローグと「トロイア滅亡」との関わり (2)『農耕詩』第1巻(穀物)プロローグと「A. 2.307-308 inscius (pastor)」との関わり (3)『農耕詩』第1巻(穀物)G. 1.325と「A. 2.306」との、詩行の、語句(後半)および韻律(全体)の共有 (1)『農耕詩』第1巻(穀物)エピローグ(G. 1.500-502)と「トロイア滅亡」との関わり G. 1.500-502において示されるのが、①トロイア滅亡の理由(ラーオメドーンの神々に対する偽誓への罰)、②この罪の血の償いにおいて、トロイア滅亡は始まりにすぎず、アウグストゥスによってようやく終わるであろうほどに神々の怒りは長く続いたことである。 韻律的には、上記②を示すG. 1.501の主韻律が『アエネーイス』全巻の主題を担う冒頭行(A. 1.1)と同一の「DDSSDS」である。内容にも同一性があると考えると、A. 1.1の「Arma」と「virum」とは、アエネーアースのみならず、彼を最初の者「quī prīmus」とする、アエネーアースからアウグストゥスに至るローマの、全てのそれらの象徴としての、「戦争」と「勇士」であることが示唆される。 ※G. 1.500-502および、参考として、アウグストゥスにかける人間世界の平和への切なる希求を歌う後続行503-505の和訳を以下に記す。 【500 [神々よ] なんとしてでも (saltem) 、この若者が(hunc iuvenem)破滅的に混迷した(ēversō)この時代を(saeclō)救うために駆けつけることを(succurrere)】、【501 妨げないでください(nē prohibēte)!我らは、今となっては既に十二分に長い時間(satis iam prīdem)、我らの血で(sanguine nostrō)】、【502 ラーオメドーンのトロイアの(Lāomedontēae Trōiae )偽誓の罪を(periūria)償ってきているのだ(luimus)。】 【503 今となっては既に長い間(iam prīdem)、天の王宮は(caelī rēgia)、我らに(nōbīs)あなたを(tē)、カエサル[オクターウィアーヌス=後のアウグストゥス]よ(Caesar)、】、【504 与え渋ってきた(invidet)のだが[=今や、このように、ようやく我らはあなたを与えられている]。[今や]、さらには(atque)、天の王宮自体が[acc+inf.のaccたるsēが省略されている]、人間世界の(hominum)、[頻発する]戦争の勝利を(triumphōs)、取り計らうこと[の多さ]に(cūrāre)不平を言っている(queritur)。】、【505 それというのも(quippe)、人間世界では(ubi [hominēs 人間世界])神の定めた正義(fās)と(atque)不正義が(nefās)逆転しており(versum)、世界中で(per orbem)かくも多くの戦争が(tot bella)起こっている(sunt[省略されている])のだから。】 (2)『農耕詩』第1巻(穀物)プロローグと「A. 2.307-308 inscius (pastor)」との関わり A. 2.307の「stupet inscius」はA. 7.381「stupet inscia suprā」と同義であり、共通的に使われる「inscius -a -um」は、 G. 1.41の「ignārus -a -um」と同義である。すなわち、「しらない、気付かない」ではなく「無知の、未熟な| ignorant, unskilled, inexperienced [OLDによる]」である。神の哀れみを受けるべき、優れた兵士であったが退役し農耕の道には未熟な者をもって、優れた勇士であるがこれからの神意の道には未熟なアエネーアースを例えたことになる。 【 A. 7.381 [革のむちで駆動されたそれ[コマ]は] 曲がりくねった(curvātīs)コース(spatiīs)で進められる(fertur)。いまだかつて(suprā)経験したことがなく(inscia)幼年でもある(impūbēsque)一団は(382 manus)呆然とする(stupet)、】、【382 回転する(volūbile)コマに(buxum)驚いて(mīrāta)。】 【G. 1.41 [25 カエサルよ、]また(que)、農耕の(agrestis)道(viae)を経験したことのない者達を(ignātōs)哀れんで(miserātus)私とともに(mēcum)】、【42 関与してください(ingredere)。そして(et)神への誓約とともに(vōtīs)名を呼ばれることに(vocārī)まさに今から(jam nunc)慣れてください(adsuesce)。 ※なお、Il. 20.86-102および176-198によれば、アエネーアースは一人イデ山中で牛の群れとともにいたところをアキッレースに襲われ、ユッピテルの助けで逃げたとされる。つまりアエネーアースは、イデ山でのエピソードによって、A. 2.308でpastorに例えられる背景を持っていたのかもしれない。 (3)『農耕詩』第1巻(穀物)G. 1.325と「A. 2.306」との、詩行の、語句(後半)および韻律(全体)の共有 A. 2.306 sternit agrōs, sternit sata laeta boumque labōrēs|| DSDDDS|APPAAA G. 1.325 et pluuia ingentī sata laeta boumque labōrēs|| DSDDDS|APPAAA A. 2.306:(山からの激しい水の流れが)畑をなぎ倒す、豊かな実りをなぎ倒す、牛たちの労苦の成果を G. 1.325:そうして雨は膨大な量で豊かな実りを牛たちの労苦の成果を(流し去る) 上記のような明白な結合によって、G. 1.325を取り巻く文脈がA. 2.306を取り巻く文脈へ参照される。 例えば、豊かな実りを壊滅させる主体は父神ユッピテルに他ならず、そのように、ギリシア勢の夜襲によるトロイア壊滅もユッピテルのなせる業である。※G. 1.328:父神自身が、雷雲の、真夜中の如き暗黒のただ中にいて、燃えるような(右手で稲妻をふるう)。 また、『農耕詩』第1巻(穀物)では、ユッピテルの雷雲がもたらす風・雨・雷火による破滅的災いを避けるには、天文に予兆を探るのもよいが、何よりも神々を、とりわけケレース神を崇敬せよ(1.339)と教えている。しかるに、トロイアの古よりのケレース神殿は都を出たところにあり、見捨てられさびれていた[A. 2.714](ラーオメドーンの強欲と同根の精神的退廃)。それゆえに、トロイアはユッピテルに滅ぼされたとも解釈できる。 以上
22 views • Apr 22, 2024
____________________________________